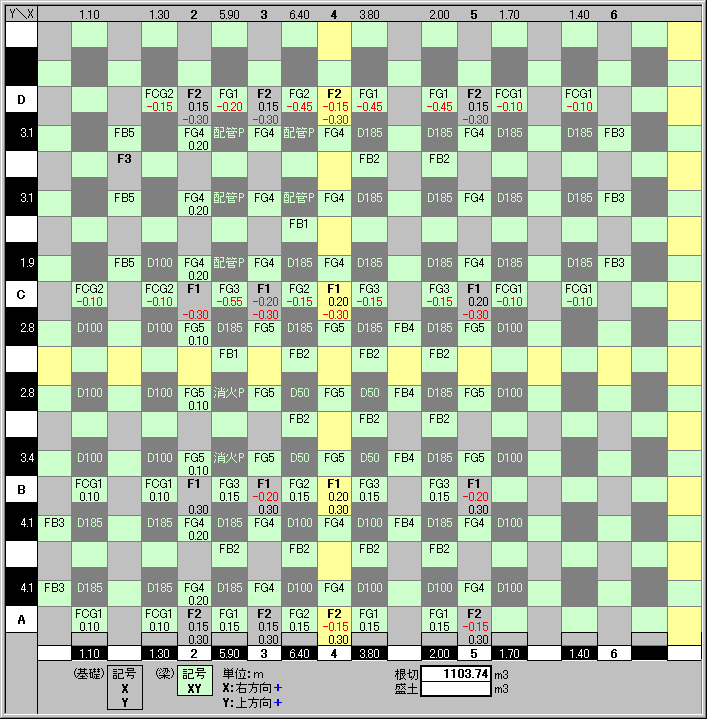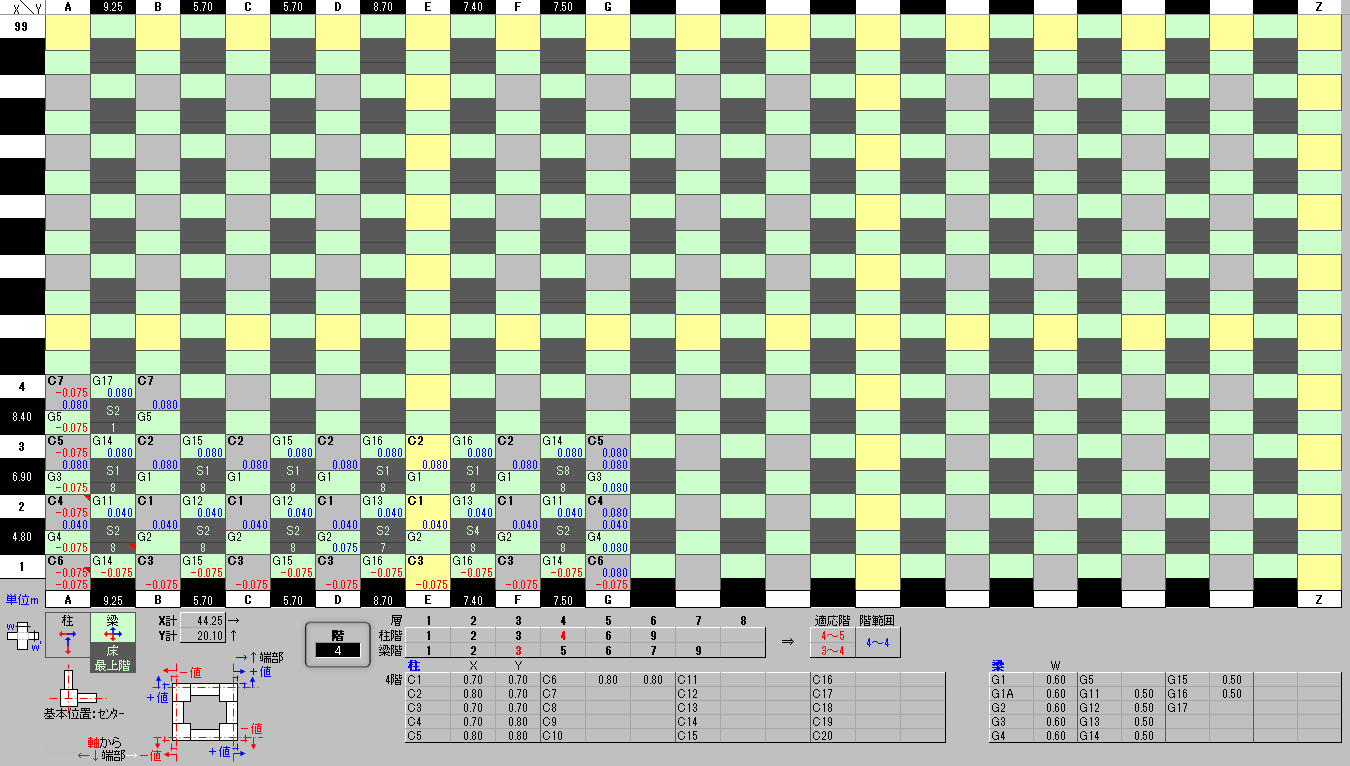| 1. | 入力データ数は、8行×20P=160行。 |
| 2. | 部材リスト ・ 端部情報は、 ドロップダウンリストより選択。 (以下、各部位共通) |
| 【断面リスト参照】ボタンより、「断面リスト」ファイルを並べて表示し、 リスト名を複写利用。(柱、大梁、小梁) |
| 3. | 【P1】~【P20】ボタンクリックにより、各ページを計算・集計。 ※ 印刷チェック → 印刷プレビュー (以下、各部位共通) |
| 【全ページ計算】ボタンで一括全計算。 |
| シート[断面]および[拾い]の入力(修正)があった場合、 終了時に【全ページ計算】の確認が表示される。 (以下、各部位共通) |
| 上下階の入力情報が当階数量に影響するため、変更時は【全ページ計算】が望ましい。 |
| 4. | [階~階]は、該当階範囲を選択。 各階に同数量が集計される。 (以下、各部位共通) |
| 単独階の場合は、 左右どちらかのみ入力も可。 たとえば [ ]~[1] (以下、各部位共通) |
| 5. | 階高『H』による算定。 但し、基礎階コンクリート・型枠=[階]-[基礎]、 地中体積=[GL]-[基礎]。 ※[GL][基礎]は基礎階のみ入力 |
| 6. | 基礎柱鉄筋は柱脚本数にて算定。 |
| 7. | 『上・梁成』により仕口部フープ本数が計算され、下部本数と合計される。 ※スパイラル仕口部 → 一般フープ、 溶接 → 全て溶接 |
| 8. | 『上下・梁成』により定着鉄筋長を判定する。 L2 or 梁成+余長 |
| 9. | 『位置・端部』には端部情報 上図1~4 より選択。 『H』に対し下記選択による増減。 !! 基礎柱+1m、最上階-1m、中間-1+1=0 が基本 |
| |
- 基礎階 :+下部余長150mm、 上階連続:+1m
- 定着 :+L2
- 連続 :±0 上階本数が多い上階筋:+1m(+1mからを補正)+(下階定着L2 or 梁成+余長)
連続 :±0 下階本数が多い下階筋:-1m(+1mまでを補正)+(上階定着L2 or 梁成+余長)
- 最上階 :-1m
|
| 10. | 柱脚頭で本数の違う鉄筋: H/2+余長 +(上階連続:+1m、下階連続:-1m) |
| 11. | 鉄骨造基礎柱では、『下』=1 (基礎階)、『上』=4 (最上階)、 柱頭補強を計測(柱リストにて径・本数を設定) |
| 12. | 圧接ヶ所は積算標準による。 (以下、各部位共通) |
| 径違い圧接に対応。 ※ 梁の径違いは定着とした |
| 圧接の2段落ちについて・・・・・圧接は径の1段落ちまでである。(共通仕様書) しかし、2段落ちが発生した場合、数量集計上、1段落ちの数量に加算することとした。 |
| (計算書には2段落ち数量が参考表示されるが、3段落ちは表示しない。) |
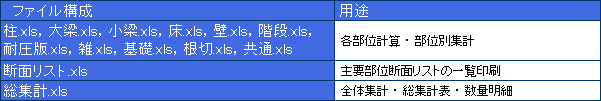
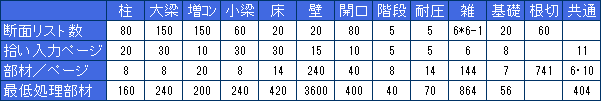
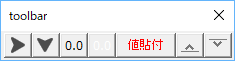
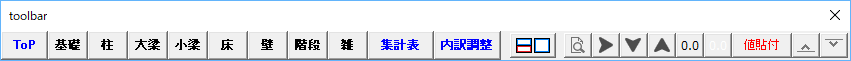
 水平整列
水平整列  プレビュー
プレビュー  セル移動
セル移動  0表示
0表示  リボン表示
リボン表示 V6.0(2022.9) H9.12~ goto myhomepage ksekisan
V6.0(2022.9) H9.12~ goto myhomepage ksekisan
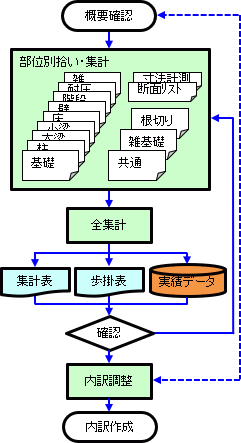
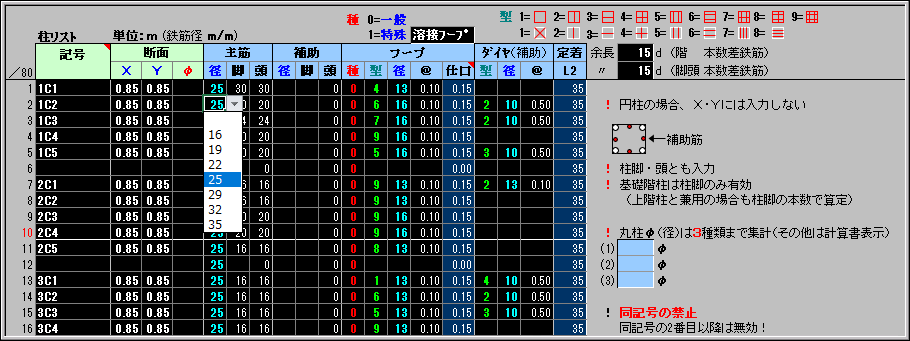
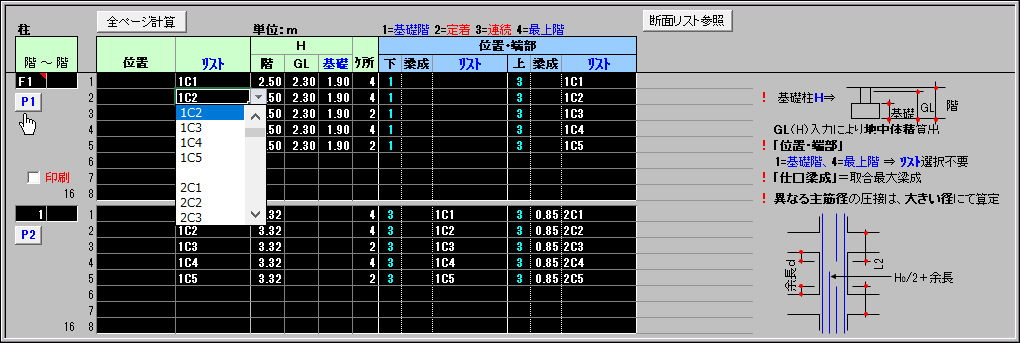
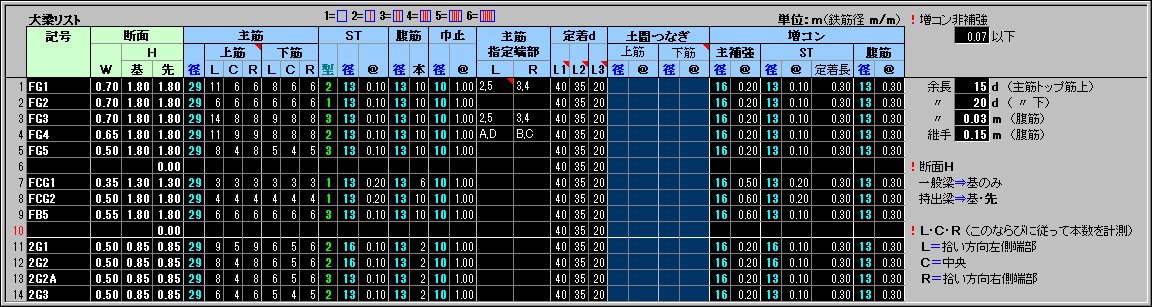
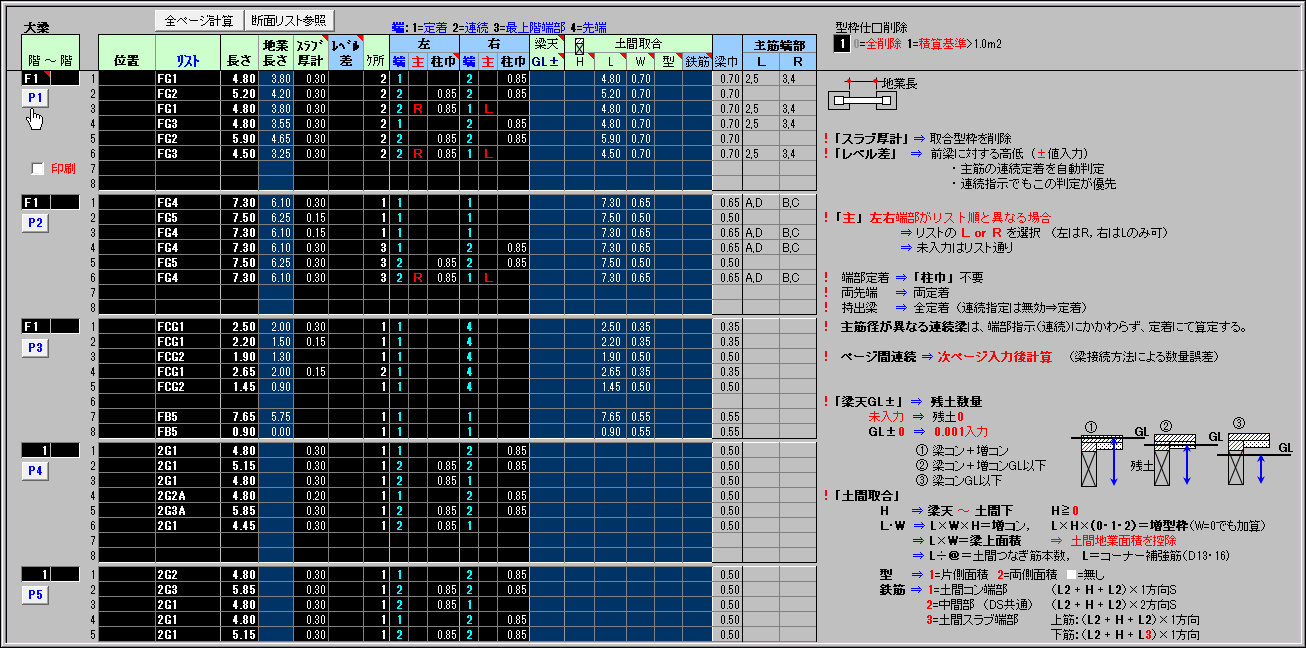
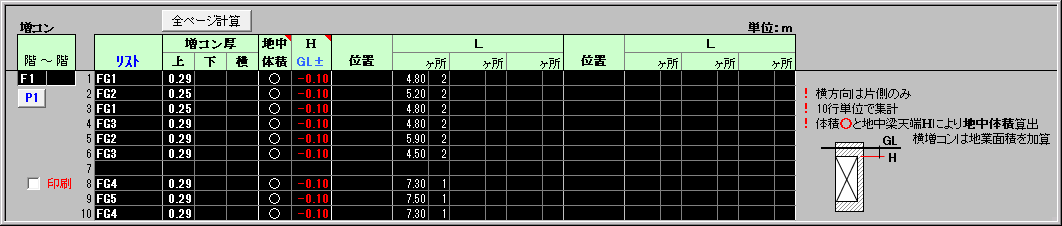
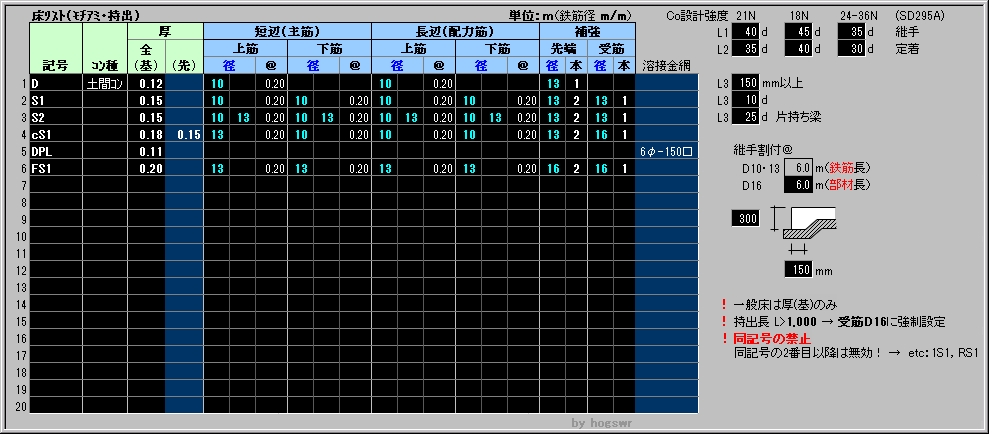
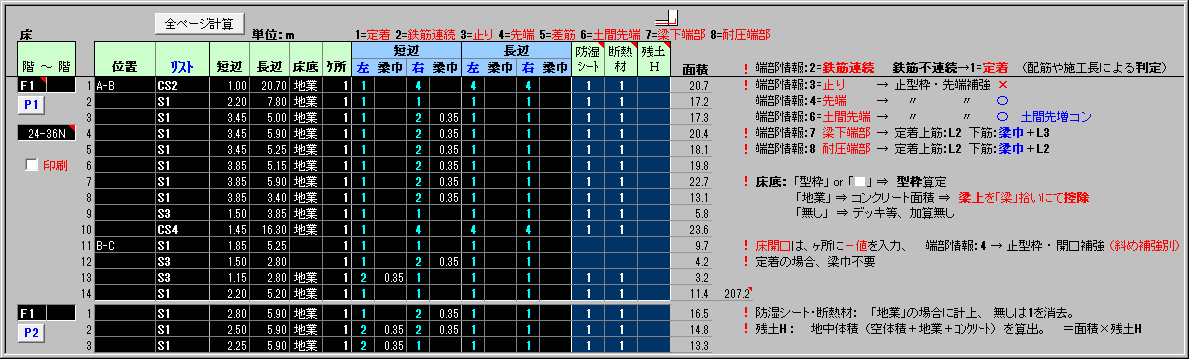
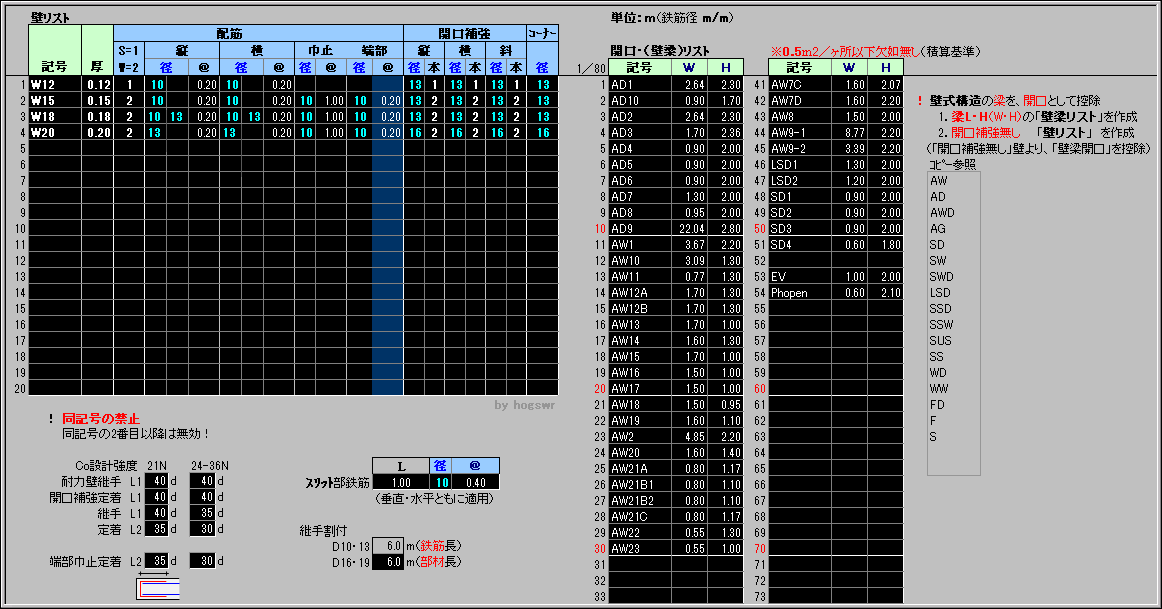
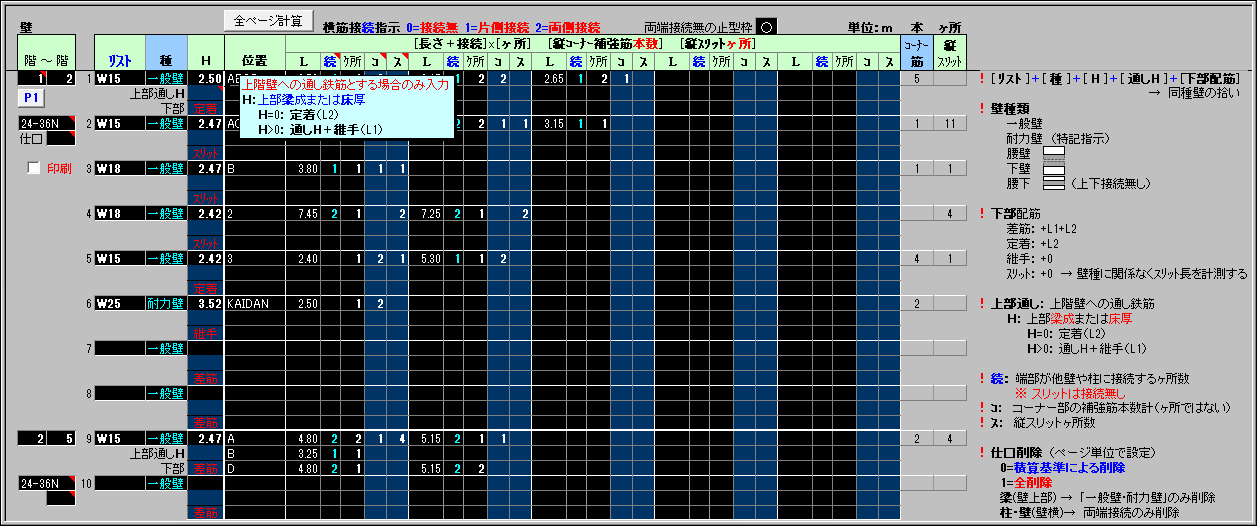
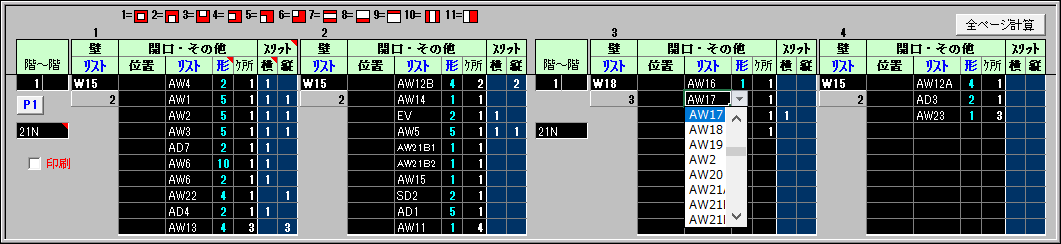
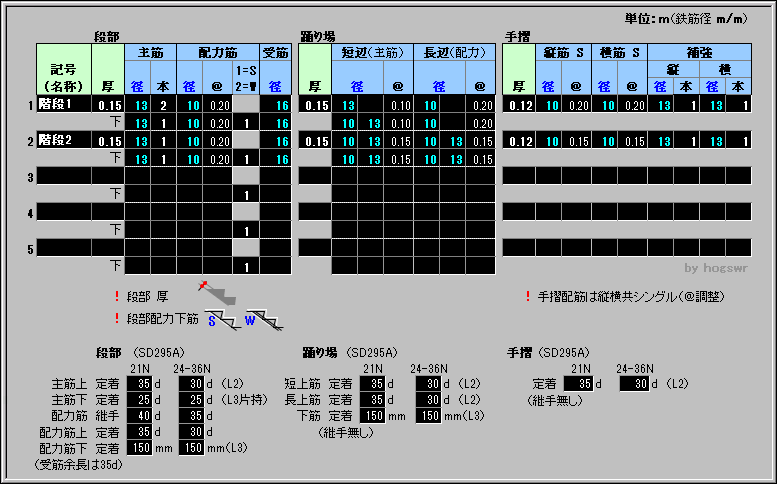
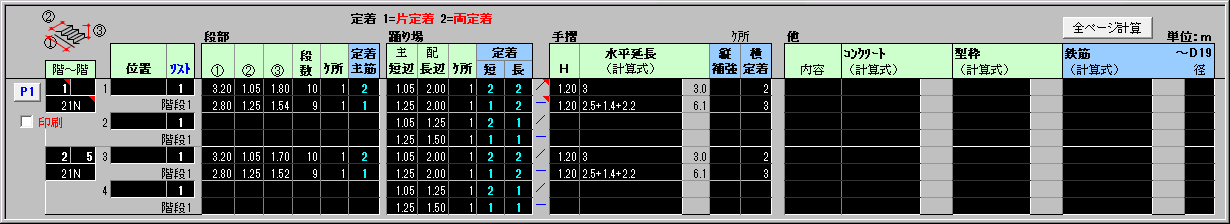
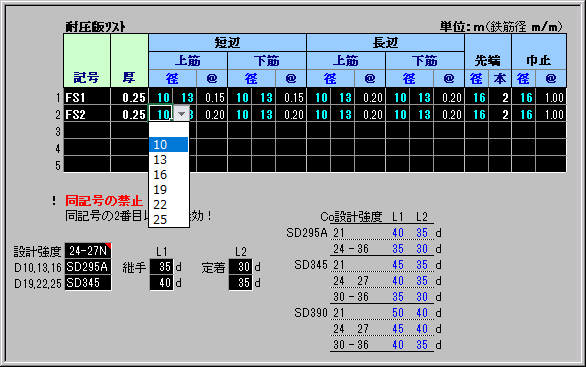
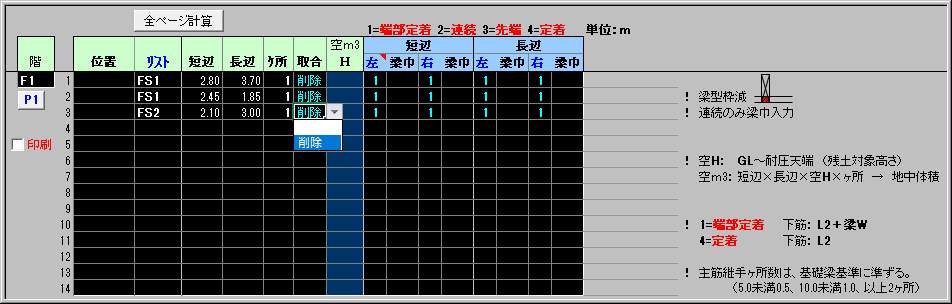
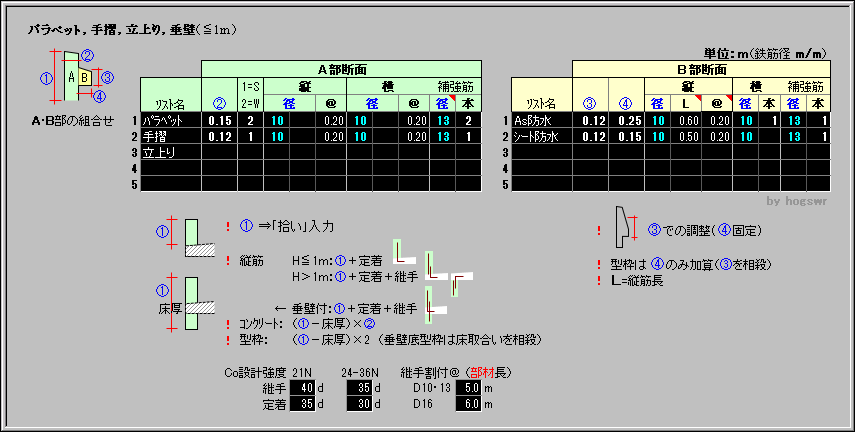
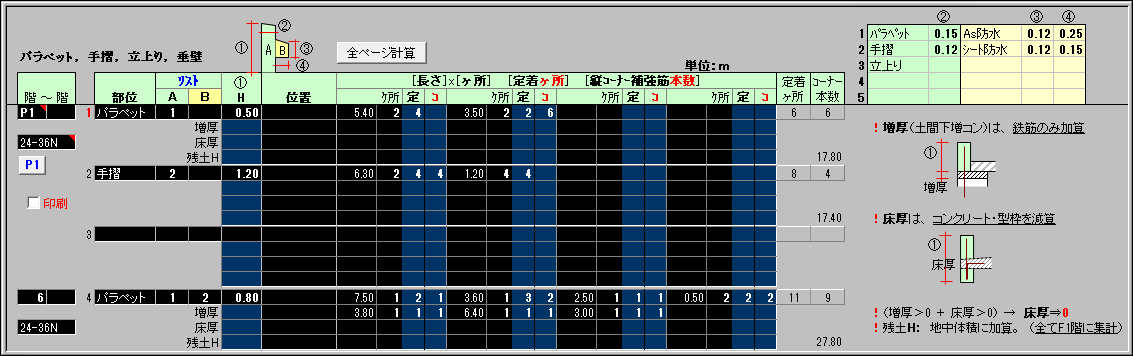
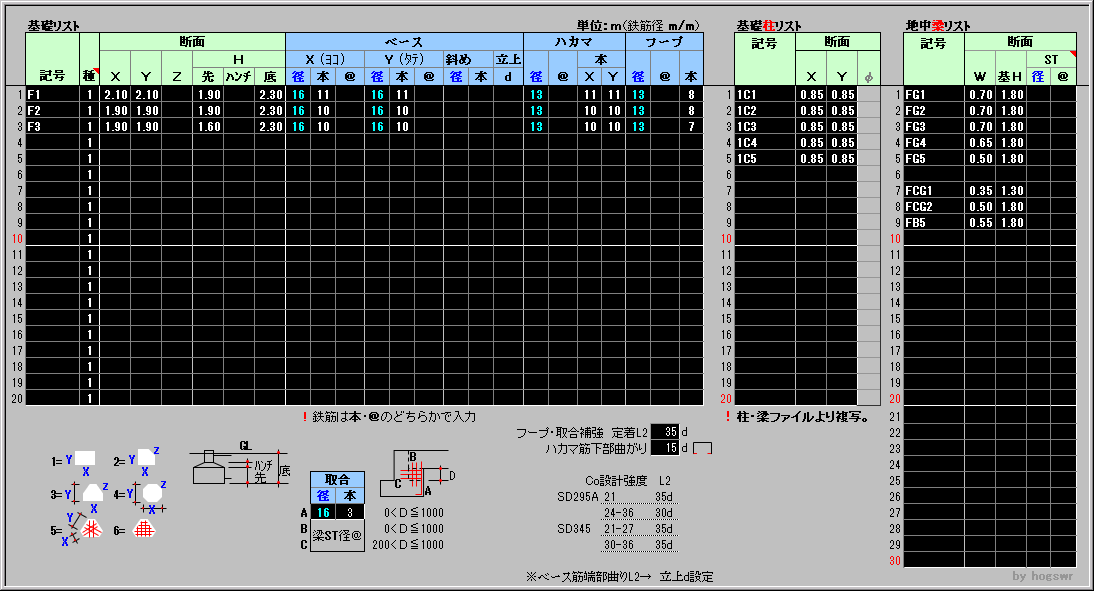
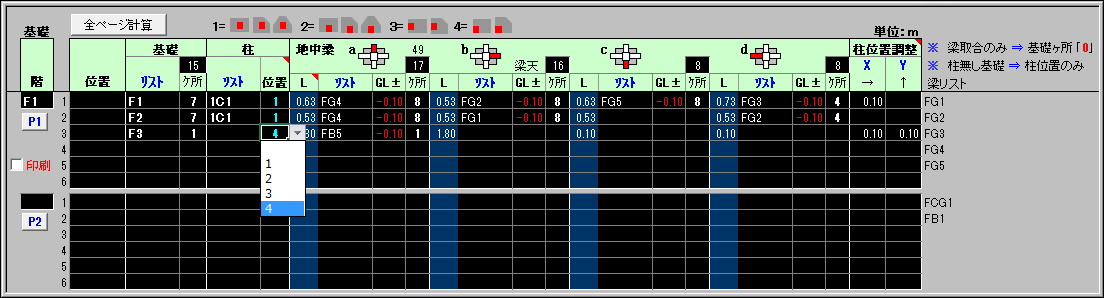
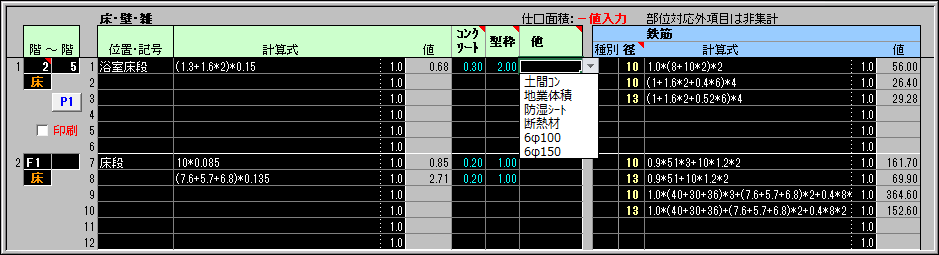
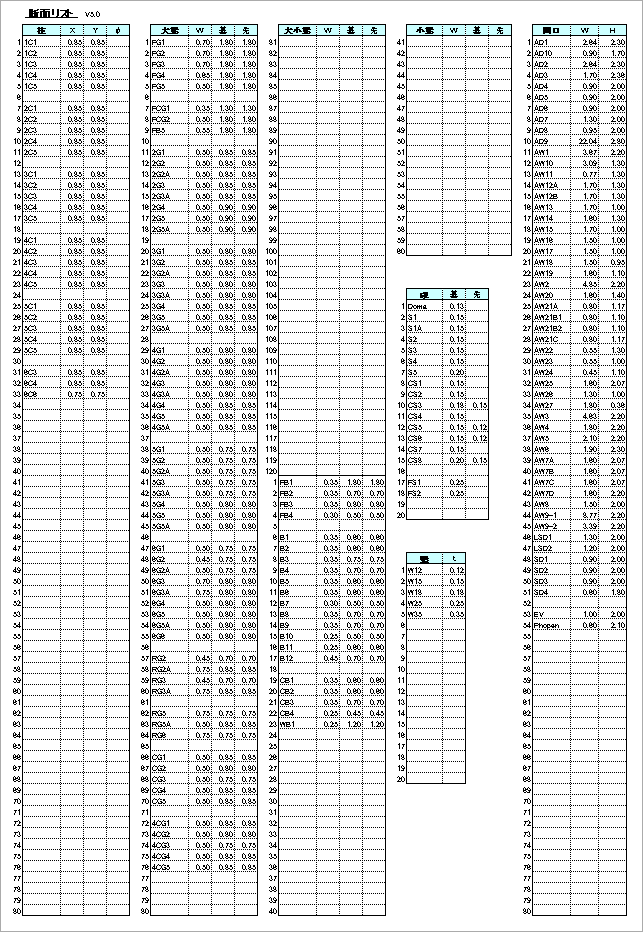
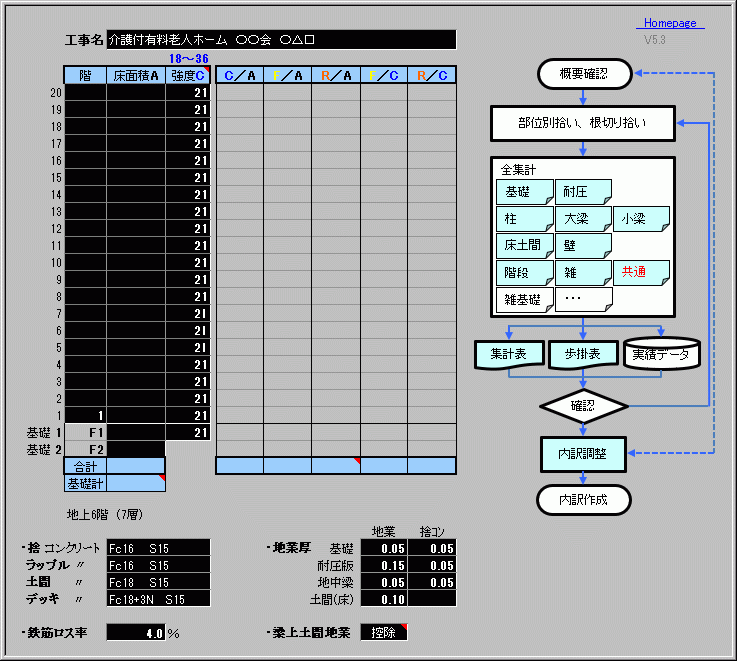
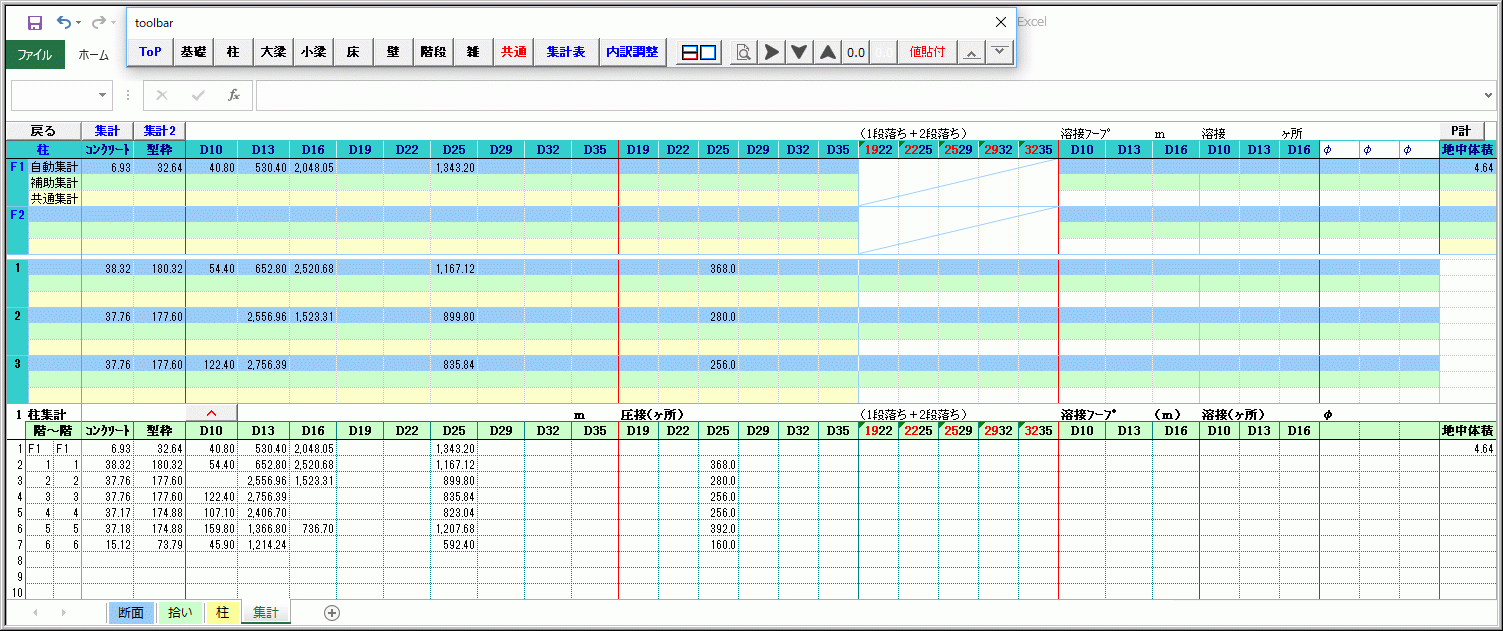
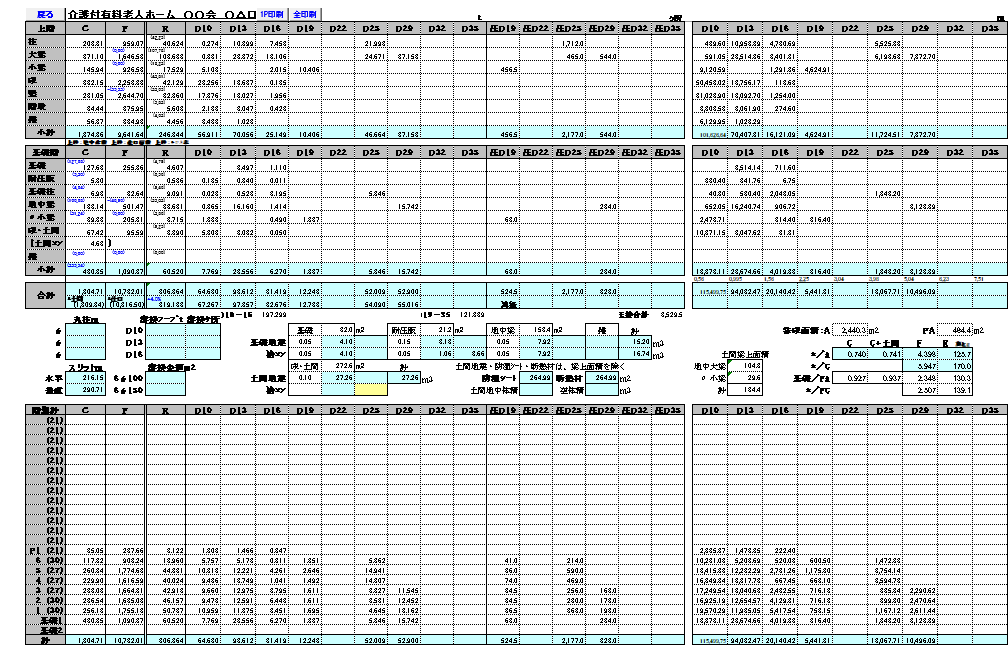
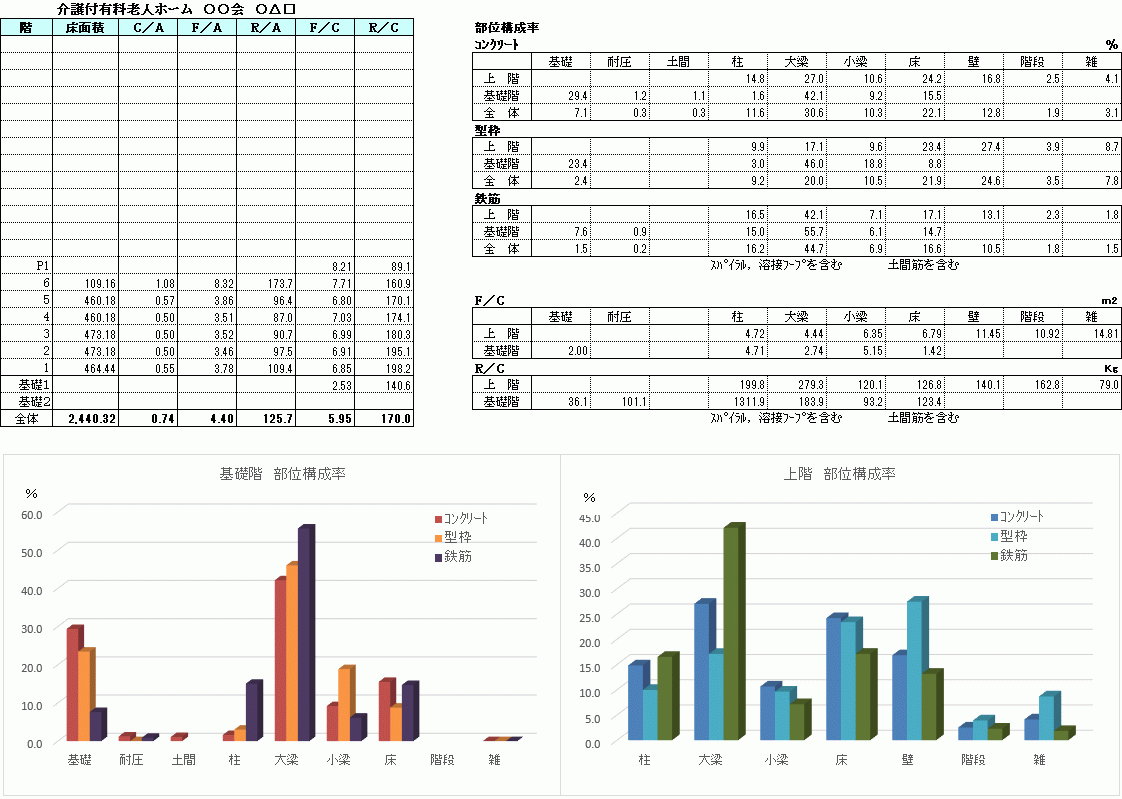
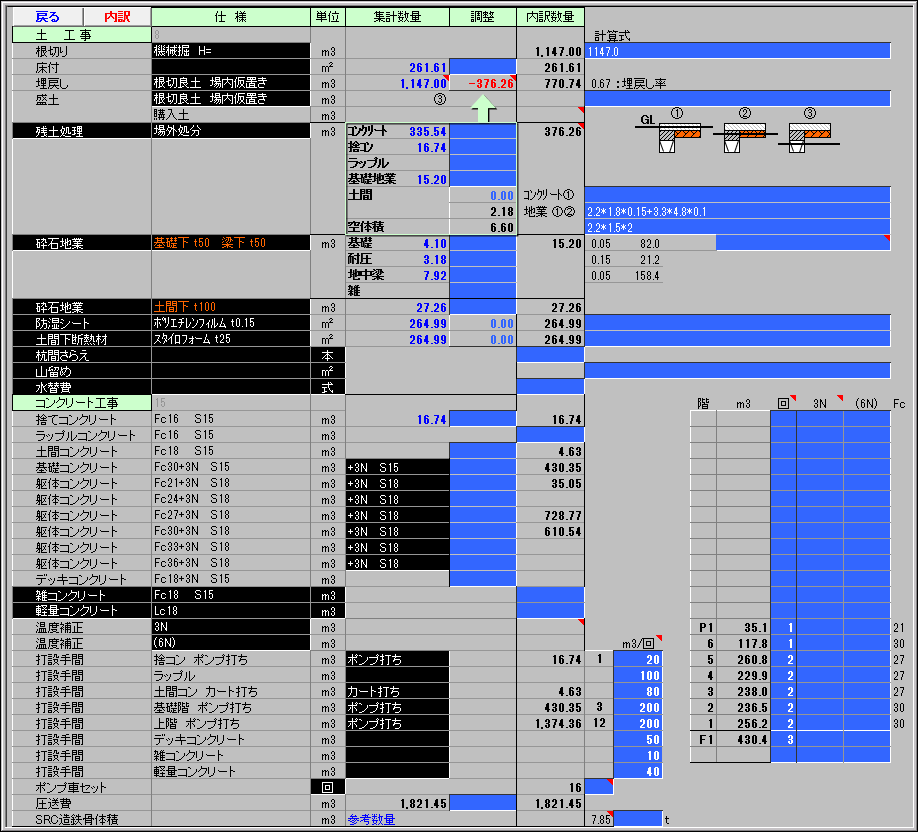
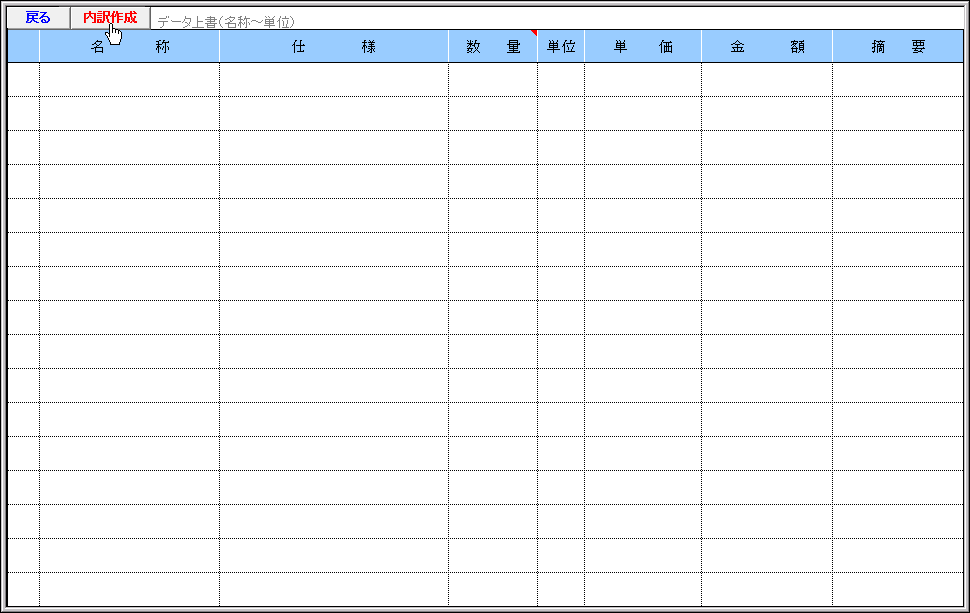
 同Hで▲加算し数量調整する。
同Hで▲加算し数量調整する。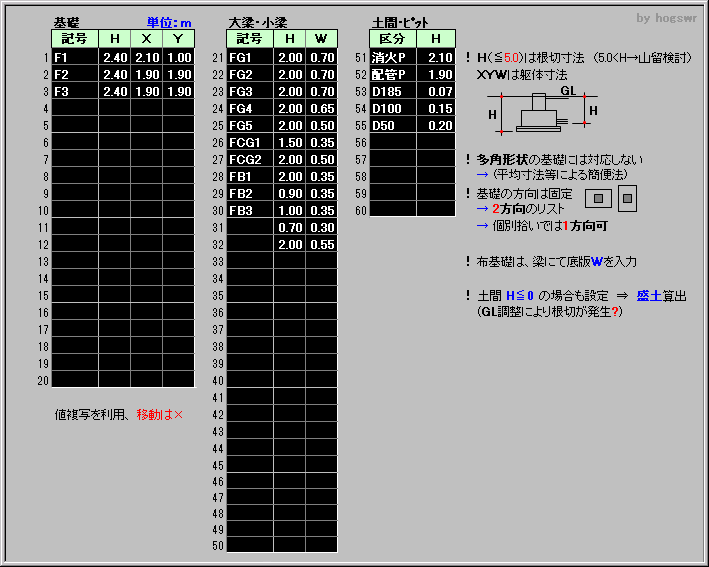
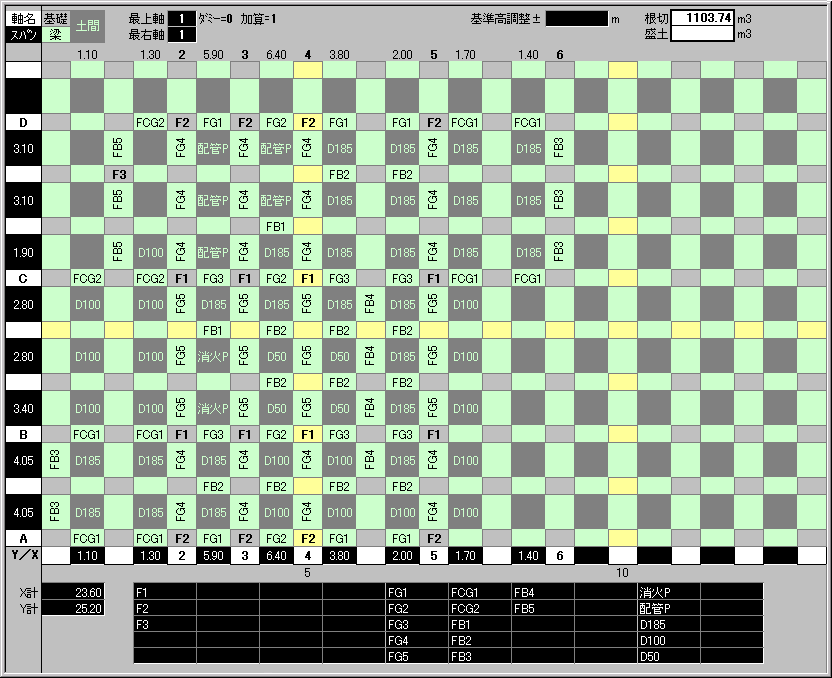
 には対応しない。 (
には対応しない。 (